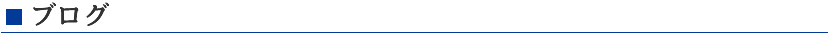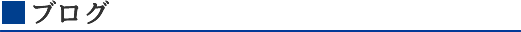【相続税対策】教育資金の都度贈与には贈与税はかからない
沖縄県那覇市の税理士、渡嘉敷です。

相続税対策のひとつとして、祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度がありますが、別にこの特例を使わなくても祖父母からの教育資金には贈与税はかからないのです。
贈与税がかからない場合
国税庁のサイトで贈与税のかからない場合ということで次のように掲載されています。
「扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」
祖父母は孫の扶養義務があるのか?という疑問もあるかと思いますが、相互に扶養の義務あるんです。(民法877条1項)
したがって、祖父母から孫への教育資金の贈与には贈与税はかからないのです。
教育資金の一括贈与の特例の意味
それでは、祖父母からの教育資金贈与の特例は何の意味があるのか?となりますが、「一括贈与」となっているところに意味があります。
贈与税がかからないとされている教育資金の贈与は、必要な都度、直接、贈与した場合に限られます。
ですので、教育資金を一括で贈与した場合は贈与税の対象になります。
このための特例なのです。
どのように教育資金を贈与したらいいのか?
祖父母が元気なうちは、入学金や授業料を祖父母の口座から直接振り込んでもらうといいでしょう。
祖父母が高齢になり、将来の健康状態に不安がある場合には特例を使って一括で贈与するとお互いに安心できるのではないでしょうか。
ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税
沖縄県那覇市の税理士、渡嘉敷です。

何かと話題のビットコインですが、国税庁はタックスアンサーで「ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係」を公表しました。
基本は雑所得
タックスアンサーでは、まず次のように掲載されています。
ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。
ビットコインで決済OKのお店も増えてきています。保有していたビットコインで支払った場合、その時点での損益を計算する必要がありそうです。
- 1BTCを10万円で購入
- その後、値上がりして1BTCが50万円になった
- 1BTCで商品を買った
このような例だと、40万円の利益が生じたことになり課税の対象になるわけですね。
所得区分については「原則として、雑所得に区分されます」と明記されました。
カッコ書きの意味するものは?
タックスアンサーを見て、何度か読み直したのがこの部分です。
(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)
邦貨とは円のことでしょう。外貨とはビットコインを含むその他の仮想通貨を指していると思います。
これは何を意味しているのでしょうか?
「ビットコインを使用することで生じた利益」=(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)
仮想通貨同士の売買を想定しているとすると、
- 1BTCを10万円で購入
- その後、値上がりして1BTCが50万円になった
- 1BTCで別の仮想通貨(イーサリアム)を購入した
このような例だと、ビットコインが値上がりしたことでイーサリアムを購入できたので、そこに40万円の利益を認識することになります。
雑所得の例外
ということで、ビットコインによる利益は原則として雑所得になりますが、例外があります。
ビットコイン決済OKのお店を営んでいる人がいたとします。
- お客さんから10万円の商品の対価として1BTCを受け取った
- その後、値上がりして1BTCが50万円になった
- 1BTCを売って50万円を得た
このような例だと、利益の40万円は雑所得ではなくて事業所得でOKということですね。
まとめ
2017年にビットコインで利益を得た人は、雑所得で申告することになります。
私が持っているビットコインも今年中に売って、来年の確定申告ではビットコインの利益を申告してみたいですね。
仮想通貨に関しては、VALUなど新しい動きが出てきているので今後は法改正もあるかもしれません。
引き続き注目していきたいと思います。
相続の話は難しい
沖縄県那覇市の税理士、渡嘉敷です。

沖縄では9月3日〜5日は旧盆でした。
5日は「ウークイ」で親戚が集まって楽しい時間を過ごした方も多いと思います。
久しぶりに親子全員が集まるので相続の話を持ち出したい・・・という相談がありましたが、これがなかなか難しい。
「相続」という言葉に拒否反応を示す親も少なくないでしょう。
総論賛成でも各論になると不穏な空気が流れることも・・・。
せっかくの楽しいウークイの場が凍りついてしまう事になりかねませんので、どこまで具体的な話をするのか?で悩んだ方も多いと思います。
一般的に「相続対策」というと
- 争続対策
- 相続税対策
- 納税資金対策
に分けることができます。
それには
- 財産を洗い出して
- 評価して
- 分け方を決めて
- 税額を計算する
という段取りが必要になってきますが、最初の「財産を洗い出す」ことでも難航します。
土地建物は分かりやすいですが、現金預金がどれだけあるか?ということはなかなか言いたくないものです。
しかも、相続税対策は「財産を減らす」「財産の価値を減らす」ことも多いので納得しない親も多いでしょう。
相続対策は親の理解なくしては進まないのでホントに難しいです。
今年の旧盆はどこまで相続の話ができましたか?
記帳くんCloudを使ってみた
沖縄県那覇市の税理士、渡嘉敷です。

会計ソフトがどんどんクラウド化していきます。
今まではfreeeやMFクラウドといった新規参入の会社が主流でしたが、既存の会計ソフト会社もクラウドに対応してきました。
ミロク情報サービス
私の事務所はミロク情報サービスという会社の会計ソフトを使っています。
クライアントの規模に合わせて数種類の会計ソフトがありますが、個人や中小企業向けの会計ソフトに「記帳くん」というのがあります。
この「記帳くん」が進化して「記帳くんCloud」というクラウド型のソフトができました。
記帳くんの機能
「記帳くんCloud」は、インストール型の「記帳くん」とほぼ同じ機能を有しているので、乗換えてもそんなに違和感なく使えると思います。
会計ソフトとしての基本的な機能は備えていて、部門管理や検索もしっかりしています。
税理士事務所とはインターネットを介してつながっているので、リアルタイムで相談ができるのもいいです。
普通に入力できる
freeeの入力方法は「収入」「支出」、「完了」「未決済」という区分になっているので、借方/貸方で考える人にとっては、とっつきにくい面もあります。
しかし、記帳くんCloudは、従来の会計ソフトと同じように借方/貸方で入力できるので、この点では入力しやすいといえるでしょう。

今後はどうなる?
既存の会計ソフトメーカーがクラウド対応したことで、ますます会計ソフトのクラウド化が進んでいくことと思います。
しかし、freeeとミロク情報サービスの目指す世界はちょっと違うようです。
freeeはERPという従来の会計ソフトの概念を超えたバックオフィス全体の効率化を目指しています。
ミロク情報サービスは、現在の税務・会計ソフトをクラウド化して税理士とクライアントの利便性を高める、というコンセプトのようです。
(ERPパッケージは別商品あり)
それぞれのソフトがどのように進化していくか楽しみです。
デジタル契約書を使ってみた
沖縄県那覇市の税理士、渡嘉敷です。

新しいクライアントと契約を結ぶ場合、今までは紙の契約書を作成していましたが、はじめてデジタルな契約書を作成してみました。
cloudSign
クラウドサインというデジタル契約書をサポートするサービスがあるので、こちらを利用します。
PDFで作成した契約書をアップロードして、契約の当事者が承認したことをCloudSignの電子署名を施すことにより証明するというものです。
弁護士ドットコム株式会社が運営しているので、怪しいものではありません。
デジタル契約書締結の手順
まず、契約書を作成します。Wordなどワープロソフトで作ってPDFに変換しておきます。
このとき、紙の契約書の定番である文言を次のように変えておくとよいでしょう。
本契約締結の証として、本書を電磁的に作成し、双方にて署名捺印又はこれに代わる電磁的処理を施し、双方保管するものとする。
契約書をアップロード
▼PDFに変換した契約書をCloudSignにアップロードします。

契約相手先の設定
次に契約の相手先のメールアドレスを入力します。
このメールアドレスで本人確認を行っているので大切なポイントになります。
また、アクセスコードというパスワードを設定することもできるので、メールアドレスだけでは不安な場合にはアクセスコードを設定します。
擬似的な署名と押印
次に「フリーテキスト」と「押印」を設定することができます。
本来、デジタル契約書には署名も押印も必要ないのです。
この機能は、今までの商慣習にあわせた擬似的なものですので、証拠力と直接的な関係はありません。
送信
最後に内容を確認して送信するだけです。
紙の契約書を作成する場合と比較してかなり時間が短縮できます。
契約相手先の承認
これで契約相手にメールが届き、その中にあるリンクをクリックして契約書を確認します。
内容に問題がなければ「承認」ボタンを押して契約完了となります。
契約書(PDFファイル)にはCloudSignによる電子証明書が付与されているので、契約が成立したという証拠になります。
電子証明書は人間の目で見ることができないので、CloudSignが発行する「合意締結証明書」により確認することができます。
まとめ
「電子契約しましょう」と言うと、ほぼ確実に戸惑いの表情を見せます。
今回もパソコンの画面を一緒に見ながら説明して承認のボタンをクリックしていただきました。
そして紙に印刷して「合意締結証明書」と一緒に保管していただくことに・・・。
まだまだデジタル契約書は一般的ではありませんが、機会があれば積極的に活用していきたいと思います。